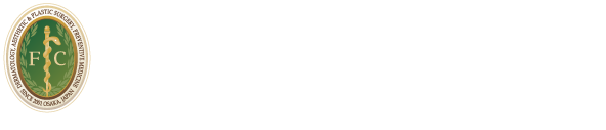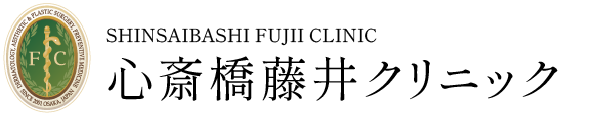こんなお悩みはありませんか?
- 包茎で悩んでいる
- においや蒸れに悩んでいる
- サイズに自信が持てない
- 性行為に支障がある
- 人前で裸になるのが恥ずかしい
- パートナーを喜ばせたい など
男性器の形成について

男性器の形成は、包茎や陰茎のサイズなど、男性器に関する機能的・審美的なお悩みを広く解決するための美容外科手術です。大阪市中央区の心斎橋藤井クリニックでは、患者様の状態や希望に応じて、包茎手術、長茎術、シリコンボール挿入など、様々な治療法をご提案いたします。
デリケートな部位だからこそ、専門医による安全で確実な施術が重要です。豊富な経験を持つ形成外科専門医が、カウンセリングから術後のケアまで一貫して担当し、傷跡の目立たない理想の仕上がりを追求いたします。
男性器の形成の種類
包茎手術(仮性包茎・カン頓包茎・真性包茎)
仮性包茎は手で剥くことが可能な状態、カン頓包茎は勃起時に強い痛みを伴う状態、真性包茎は全く剥くことができない状態を指します。それぞれの状態に応じて余分な包皮を切除することで、男性器の機能面を改善させつつ自然な形に仕上げます。
真性包茎、カン頓包茎、排尿障害、腎機能障害、繰り返す包皮炎や亀頭炎を呈している方など、男性器の機能が障害されている場合には、健康保険が適用可能なこともあります。
※小学生高学年、中学生でも治療は可能です
長茎術
長茎術は、陰茎を長くさせる手術です。サイズへのコンプレックスを抱えておられる方は、長茎術によって解消が期待できます。体内に埋まった陰茎を外へ引き出す(埋没陰茎長茎手術)、ペニスの付け根の脂肪を吸引する(脂肪吸引式長茎手術)、特殊な薬剤(リパス)を注入して陰茎を増大させるなど様々な術式があり、陰茎の状態に応じて選択します。
シリコンボール挿入術
医療用シリコンのボールを陰茎の皮下に挿入することで、陰茎の太さや形状を改善する手術です。専門医の確かな技術により、性行為のパートナーへの効果増強と自然な仕上がりを両立させます。
男性器の形成のメリット・デメリット
メリット
- 包茎による不快感や痛みが改善される
- においや蒸れなどが改善される
- 性行為時の支障が解消される
- 見た目の改善で自信が持てる
- 心理的なストレスが軽減される
デメリット
- 手術後の一時的な痛みや腫れがある
- 完全な回復まで時間がかかる
- 性行為を控える期間が必要
- 感染症のリスクがある(シリコンボール)
男性器の形成の流れ
STEP1
カウンセリング
医師がカウンセリングを行い、お悩みやご希望を丁寧にお聞きします。現在の状態を慎重に診察し、お悩み解決のために最適な方法とそのリスクをご説明します。
STEP2
デザイン
患者様の状態とご希望を考慮し、術後の状態から逆算してデザインを行います。
STEP3
術前準備
手術当日は、施術部位の清潔を保つため入念な消毒を行います。
その後、細い針を使用して局所麻酔を慎重に施します。
STEP4
手術
麻酔が十分に効いたことを確認した後、事前のご相談内容に基づき慎重に手術を進めます。
手術終了後は患部に包帯を巻きます。
STEP5
術後ケア
ベッドでしばらくお休みいただき、血が止まるのを待ちます。
その後、医師より清潔保持の方法や日常生活での注意点など、回復に向けた具体的なアドバイスをご説明します。
STEP6
経過観察
術後は1週間以降を目安に抜糸を行いますので、再度ご来院ください。
その後も段階的に回復状況を確認しますので、定期的な通院をお願いいたします。
施術時間・ダウンタイムなど
- 施術時間:20~1時間程度
- 麻酔:局所麻酔(施術時の痛みはありません)
- 術後の腫れ:1~2週間ほど腫れや内出血が続くことがあります。
- 痛み:数日ほど痛みが生じることがあります(痛み止めを処方します)
- シャワー・入浴の可能日:シャワーは施術翌日から、入浴は1週間後から
- 抜糸:7日目以降
- 性行為・マスターベーション:1か月程度控える(自然な勃起は問題なし)
禁忌
以下に該当する方は、事前に医師にご相談ください。
- ケロイド体質の方
- 血液凝固障害のある方
- 麻酔へのアレルギーがある方
- 性感染症に罹患している方
- 陰部に重度の炎症や感染症がある方
- シリコンなどの人工物にアレルギーのある方
- 重度の糖尿病の方
- 易感染性の全身疾患がある方
- 同部位の手術歴がある方(※要相談)
- 抗血栓薬を服用中の方
- 重度の自己免疫疾患のある方 など